市民公開講座
市民公開講座No.517
「極低温のふしぎな世界」
新井 敏一(電気電子工学科 教授)
6月4日(金)18:00~19:15
物を極限まで冷たくするといったいどうなるのでしょうか。また、どうしてそうなるのでしょうか。極低温の物質が見せる驚きの性質を、液体窒素を使ったデモ実験動画をまじえながら物理学の面から解き明かします。

HOME > 市民公開講座/その他講座関連
新井 敏一(電気電子工学科 教授)
6月4日(金)18:00~19:15
物を極限まで冷たくするといったいどうなるのでしょうか。また、どうしてそうなるのでしょうか。極低温の物質が見せる驚きの性質を、液体窒素を使ったデモ実験動画をまじえながら物理学の面から解き明かします。
令和6年度 オンライン市民公開講座を6月7日(金)より開講いたします。
本学は2024年4月、60周年を迎えました。
科学技術の急進や社会・環境の変化に敏感に対応し、東北工業大学ならではのまなびの場、より良い未来と暮らしへの知をつなぐ場を皆さまに提供してまいります。
講座はWeb会議システムZoom(ズーム)で受講いただきます。
参加費は無料です。
事前のお申し込みが必要となりますので、下記フォームからお申込みください。
(ZoomおよびZoom(ロゴ)は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。)
お申込みは講座開催日の前日17時までとさせていただきます。
開講15分前より入室可能ですので、あらかじめインターネットの接続状況をご確認ください。講座時間は講義1時間に質疑応答15分を含め1時間15分を目安としております。講座時間1時間が経過しましたら講義により早めの終了となる場合もございますのでご了承ください。受講の流れをPDFでご用意いたしましたので下記リンクよりご覧ください。
皆さまのお申込みをお待ちいたしております。
※事前にZoomアプリ(無料)をダウンロード(インストール)してください。
◆Zoomダウンロードページはコチラ(PC用)※別タブで開きます。
◆Zoomサポート※別タブで開きます。
◆Zoomテスト画面はコチラ※別タブで開きます。
Webブラウザから入られる方は、「Google Chrome」「Firefox」がおすすめです。
「Microsoft Edge」はバージョンのご確認が必要な場合がございます。「インターネットエクスプローラー」は2022年6月にサポート終了のため対応していません。ご注意ください。
ご不明の点、Zoom手順等についてのお問合せは下記までご連絡ください。
二瀬 由理(経営コミュニケーション学科 准教授)
2月9日(火) 16:00~17:15
「人は、どのような時に幸せを感じるのか」、この問題は誰もが関心を持っているものの、非常に難しい問題である。この講座では、これまで講演者らが行った調査の結果を踏まえ価値観の違いによる幸福観の違いを考察します。また、コロナ禍で会う人も行動も制限されている中で、幸福の価値はどう変わったのか考えてみたい。
佐々木 留美子(建築学科 講師)
1月19日(火) 18:00~19:15
日本の入国管理法の改定により、建設業でも特定技能外国人という新たな在留資格の仕組みがスタートした。今後、外国人材の受け入れが進むこととなるであろう。建設現場の人手不足は、海外の建設労働力によって解消されるのか。日本の技能者を取り巻く現状と、海外の技能者を送り出す国々の建設産業を俯瞰することで、建設業の未来を考えます。
小出 英夫(都市マネジメント学科 教授)
12月18日(金) 18:00~19:15
コンクリート? 鉄筋コンクリート? セメント? モルタル? まずはその違いからお話しします。また、身近な鉄筋コンクリートのスゴイところもお伝えします。このような基本的な話を中心に、コンクリートのひび割れの恐ろしさや、最近得られたコンクリートに関する実験結果を交えてお話しします。
(左写真:直接引張試験)
片山 文雄(総合教育センター 准教授)
12月12日(土) 15:00~16:15
自民党、立憲民主党、日本維新の会、共産党・・・いろいろな政党が互いに競争しながら活動しています。「政党政治」は当たり前のようですが、政治の唯一の方法でもなく、そのメリット・デメリットも実は分かりにくいのです。政党政治といえない国(例えば中国)も台頭するなか、あらためて政党政治の意味を考えます。
田倉 哲也(電気電子工学科 准教授)
12月11日(金) 18:00~19:15
電気エネルギーは非常に身近な存在として私たちの生活に深く浸透している。近年、その電気エネルギーを送る手段として、電磁波のような「波」を利用したワイヤレス給電技術が確立されてきた。本講座では、それによってどのようなことが可能になるのか、そしてその技術は安全なのかなどについて一緒に考えていきます。
加藤 善大(環境応用化学科 准教授)
12月4日(金) 18:00~19:15
再生可能エネルギーを用いた水素製造のため、真水のアルカリ水電解を行うことは水資源保護の観点から避けるべきである。このため、多量に存在する海水による直接電解を提案している。本講座では海水電解に用いる水素、酸素発生電極およびその周辺技術について説明します。
(左写真:酸素発生効率99.02%の電極、電解時間 2307 h、測定日2011.3.11)
髙野 淳司(総合教育センター 教授)
12月4日(金) 16:00~17:15
近年、子どもの発達、教育のトレンドとして非認知能力が注目されていますが、いったいどのようなものなのでしょうか?今回は、この非認知能力について、やさしく解説をしていきます。また非認知能力とつながりの深い、運動・スポーツとの関係についても検討していきたいと思います。
伊藤 美由紀(生活デザイン学科 准教授/地域のくらし共創デザイン研究所 所長)
ゲストスピーカー:就労継続支援B型事業所 希望の星 安藤 修二 氏
11月21日(土) 15:00~16:30
仙台市ホームページに「障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例ができました」とあります。障害がある方への配慮、障害に対する誤解や偏見について考えたことはありますか。現在一緒に活動し、刺激をいただいている障害がある方にもご登壇いただき「共創デザイン」を考えます。


工藤 栄亮(情報通信工学科 教授)
11月24日(火)18:00~19:15
5G、LTEなど携帯電話に関係する言葉を耳にする機会が増えていますが、一体何なのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?この講座では、これまでの携帯電話の進化の歴史をふりかえりながら、5Gについて解説していきます。
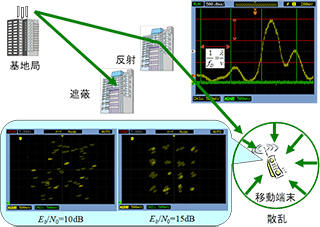
大木 葉子(総合教育センター 准教授)
11月20日(金)18:00~19:15
絵本というと「子どもの読み物」というイメージをもたれがちですが、近年、文章表現と視覚表現という二つの表現領域を総合したメディアとして注目され、その可能性の豊かさが指摘されています。本講座では、絵本というメディアの特性を知り、その表現方法を学ぶとともに、表現媒体としての豊かな可能性について考えます。