
コミュニティデザイン研究室
新井 信幸 / 教授
ARAI Nobuyuki
- 学位
- 博士(学術)
研究分野
古い建物やまち、コミュニティを持続的に活かす研究
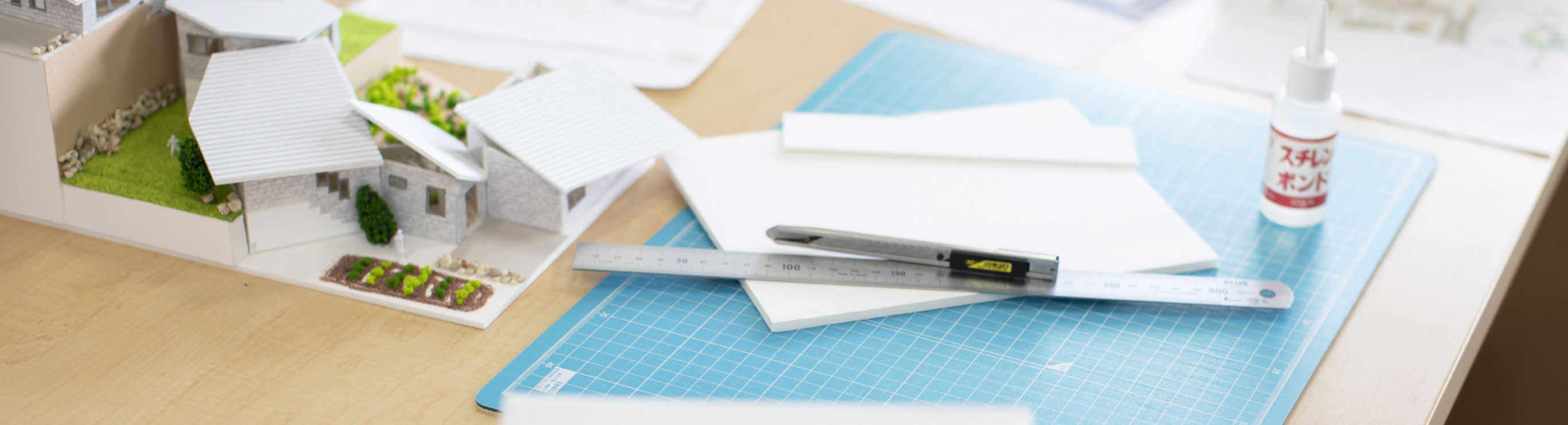


コミュニティデザイン研究室
ARAI Nobuyuki
古い建物やまち、コミュニティを持続的に活かす研究

福祉住環境デザイン研究室
ISHII Satoshi
超高齢・共生社会の暮らしを支える住宅や施設の建築計画研究

保全型地域計画研究室
FUWA Masahito
地域計画、まちづくり、景観保全、民家研究

建築史研究室
NAKAMURA Takumi
日本建築史、文化財保存修復

建築デザイン研究室
FUKUYA Shoko
建築デザイン、家具デザイン、ランドスケープデザイン

建築デザイン、建築計画研究室
SAITO Ryutaro
建築デザイン、建築計画、都市計画、地域計画

建築・インテリアデザイン研究室
NISHIKORI Maya
建築デザイン、インテリアデザイン

構造工学研究室
XUE Songtao
建築構造工学、耐震工学、制振工学、構造ヘルスモニタリングシステム

地震減災・防災研究室
FUNAKI Naoki
建築構造、地震時の建物の揺れを軽減する免震・制振機構の研究

損傷制御システム研究室
HORI Norio
建築物の地震応答・損傷の制御

知能建築研究室
CAO Miao
建築×AIから生み出す新しい融合技術を研究

構造性能維持システム研究室
HATANAKA Tomoyuki
建物の安全性と災害に強い建築構造に関する研究

建築マネジメント研究室
ARIKAWA Satoshi
建築の長寿命化を支える生産、管理、社会システムに関する研究

建築材料工学研究室
KIKUTA Takatsune
超高性能・高付加価値な先端的建築材料に関する研究

環境・防災システム研究室
KAGIYA Koji
建築・都市と装置、情報の新しい関係の構築

BIM研究室
Xu Lei
建築設備・環境、BIM、防災

建築環境学研究室
OISHI Hiroshi
都市・建築空間の環境性状と利用者の心理的評価・行動特性に関する研究