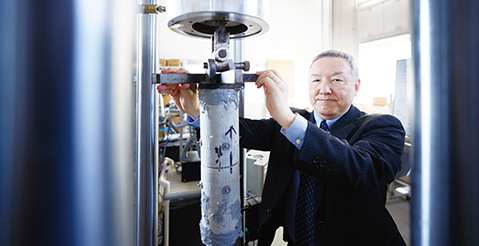PROFILE
1991年、千葉大学で工学修士の学位を取得後、キヤノン株式会社デザインセンターに勤務。1998年にフィンランド・ヘルシンキ芸術デザイン大学(UIAH)ガラス&セラミック学科、工業デザイン学科に留学した後、2000年から5年間、同国でフリーランスとしてデザイン活動も行う。帰国後、2005年4月に東北工業大学工学部デザイン工学科の講師に就任。クリエイティブデザイン学科(現・産業デザイン学科)の准教授を経て2015年4月に教授となり、現在に至る。
- 担当科目
- デザイン計画および同実習
- 表現技術および同演習
- デザイン史
- 材料学 ・生産技術
※教員の所属・役職は取材当時のものです。
THEME新たな発想から生み出される
高品位なモノのデザイン
THEME新たな発想から生み出される
高品位なモノのデザイン
人々の暮らしに寄り添い、あらゆる製品の形状や機能などの改善を追求していくプロダクトデザイン。そのプロセスには、人々の行動や社会・文化の動向からあるべき生活の姿を思い描くイマジネーションの力と、知識・技術を駆使して目に見えるかたちにする造形力が求められると説く梅田先生。そのために、自らの感性を高め、思い描くカタチを実体にすることができる表現技術の研鑽を学生たちに指導しています。

シンプルながら革新性を秘めるフィンランドのデザインに傾倒
フィンランドで学ぼうと思った理由とは。
当時日本で人気があったのは、イタリアなどの華やかなデザインでしたが、ひねくれ者の性分から、自分はもっと違う国で学んでみたいと思っていました。フィンランドのデザインは、奇をてらわずに合理性を生真面目に突き詰めているのに不思議な詩情が漂うというか、逆説的ですがそこに斬新さを感じ、これこそが自分が目指すべき方向性だと確信しました。北欧デザインは無駄のないシンプルなスタイルを評価されることが多いですが、フィンランドのデザインはそこが一味違うと思います。
留学先でどんな学びを得られましたか。
留学したヘルシンキ芸術デザイン大学では、学位の取得を第一とするよりも、さまざまな分野のプログラムに参加できることに魅力を感じました。もちろん、ヨーロッパならではのプロダクトデザインを学ぶことも目的ではありましたが、アーティスティックな一点物から大量生産され一般に流通する日用品まで幅広く手掛けるガラス・セラミックの領域に、キヤノンでの勤務経験など私のバックグラウンドが活きる世界だと感じ、熱中して取り組みました。
社会や文化の動向に目を向け世の中にあるべき形を生み出す力
本学で得られるプロダクトデザインの学びとは。
本学科では、さまざまなデザインの領域に触れることができ、十分な知識や情報を得た上で自分が学びたい方向性を選択することができます。プロダクトデザインはその中の1つの分野で、実際の素材を扱い実体のあるものを作り上げるのが特徴です。そのために、材料に関する知識や加工技術についても習得していきます。
学生はどのような学びの過程を歩むのですか。
プロダクトデザインのプロセスは、ターゲットとするユーザー像やライフスタイルなどから導き出されたコンセプトを設定し、それに対して必要なデザイン条件を挙げ、それに沿って造形を展開していきます。具体的なかたちを検討するプロトタイプの段階では、最近では3D-CADなどのデジタル技術を駆使してアウトプットする流れが主流となっています。3年生からは、コンセプトの模索を重点的に行うよう指導しており、実際の売り場などを視察してマーケットリサーチなどにも取り組んでもらっています。また、社会情勢や流行などによって人々のライフスタイルが目まぐるしく変遷していく中で、どのような新しいニーズが生まれるのかを敏感にキャッチできる豊かな感性を養うことも重視しています。
造形力を磨くためにどのような指導をしていますか。
ただ単に制作に終始するのではなく、この世の中に何があるべきかを深く考察する視点を持って欲しいと思っています。その視点から得たものを高い精度で具現化するために、スケッチの書き方や3D-CADソフトの操作といった基礎的な表現技術の習得にしっかり取り組んでもらっています。さらに、卒業後、デザイナーとして活躍したいという熱意のある3年生には、少数精鋭の「エキスパートデザイン計画および同実習」への参加も勧めています。私が担当している課題は「木製椅子のデザイン」ですが、材料やその加工技術の特性を生かしながら、いかに美しく機能的な造形を生み出すことができるかに重点を置いた実践的な内容になっています。
いつか芽吹く才能を信じながら新たなデザインを描く人材を輩出
学生に指導する上で大切にしていることとは。
大学の授業ですべてを完璧に習得することはほぼ不可能ですが、いつか大きく開花するような種のようなものを与えてあげたいと思っています。私自身がそうだったように、学生たちが仕事に就いて何年か経ち、「ああ、あの時先生が言っていたのはこういうことだったのか」と、思い出してくれればうれしいですね。
梅田先生にとっての「未来のエスキース」とは。
「未来のエスキース」を描くということは、ずばり“デザイン”そのものではないかと考えています。未来を思い描くためには豊かなイマジネーションが必要で、それこそがデザイナーが自らの中で培い続けるべき力です。そこには、人それぞれの生き様であったり経験などから学び得た知識だったりと、多彩なエッセンスが反映されます。だからこそ学生には、その素地を磨くことができる大学の学びの意義をしっかり自覚してほしい。エスキースって格好いい語感のイメージだけで捉えられがちですが、デザインを学ぶ上での本質的な意味を持っていることを学生たちに伝えていきたいですね。そして、常に先を見据えながらプロダクトデザインに臨む、その責任の重さについても思いを巡らせて欲しい。そう言いながらも、それを重荷だと思わず、新しい何かを世の中に生み出すワクワクを楽しんで欲しいとも願っています。

COLUMN

わたしと
ロック
「ぶっちゃけ」で創造の本質に迫る
ロック。音楽の一つのジャンルのあれです。小学生の時に年上のいとこからLed Zeppelin(わからない単語は調べること)を聴かされて以来、特に青春時代の人格形成期にロックからは多大な影響を受けました。その後結局ロッカーにはならずデザイナーになったわけですが、しかし思えばデザインするときにいつも頭のどこかに「それがロック的にかっこいいかどうか」という基準があったような気がするのです。それはつまり、創造に向き合うときの態度とでも言いましょうか。若いころのそれは「権威に対する反抗心」みたいなとんがった感じのものでしたが、歳とった今はもう少しマイルドに「本音でぶっちゃけて本質に迫る」ぐらいの心構えですかね。デザインにおける創造の原動力として、冗談抜きでこれは非常に重要なコンセプトだと思うので、研究室の学生に時々ロック談義を持ちかけるのですが、あまり興味を持ってもらえないのが残念です。