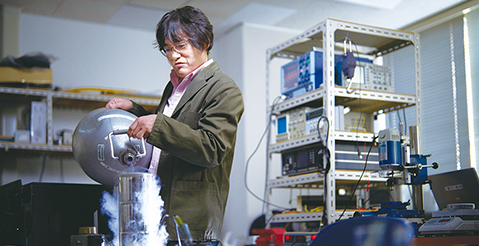PROFILE
1984年に東北大学工学部土木工学科を卒業後、同大大学院に進み、助手を務めながら1990年に工学博士の学位を取得。同年4月、本学工学部の講師に就任し、1992年に助教授、2005年に教授となり、現在に至る。2016年5月~2017年1月の期間、チェコ共和国のブルノ工科大学の客員研究員として招聘(しょうへい)され、現地で研究指導等を行う。2023年から土木学会の理事も務めている。
- 担当科目
- コンクリート
- 鉄筋コンクリートⅠ・Ⅱ
- 都市工学 実験Ⅰ(コンクリート実験)
- 都市工学デザイン (コンクリート及び鋼構造コース)
- 構造工学総論
- 鉄筋コンクリート工学特論
※教員の所属・役職は取材当時のものです。
THEMEコンクリートの引張に対する
力学的性質を実験により解明
THEMEコンクリートの引張に対する
力学的性質を実験により解明
コンクリートの引張強度は圧縮強度の1/10以下のため、かつてはあまり設計で重視されてきませんでした。しかし、高度経済成長期に数多く建設された土木構造物の老朽化が目立つようになってきたため、引張に対する力学的性質は重要な性質の一つとなっています。小出先生は、緻密なデータ採取と観察を大切にしながら、コンクリートの直接引張試験方法とその実験装置を提案。さらに、環境の課題に応えるコンクリートの未来も見据えています。

自らの学術分野を深めながら知見を広めたチェコでの9カ月
チェコの大学に客員研究員として招かれた経緯とは。
本学に海外の研究機関で長期研修できる制度があることを知り、参加を志願しました。それまで、学会などで海外に行くことはあったのですが、海外で長期間生活するような経験がなかったので、50歳を超えていましたが知見を深める絶好のチャンスだと思いました。どうせなら、日本人がほとんどいない土地に行きたいと考えていたので、チェコ共和国の第二の都市ブルノにある、ブルノ工科大学を選びました。この大学には、若い頃に国際学会で知り合ってからメールのやり取りもしていた、年齢も近いDrahomir Novak教授がおり、快く客員研究員として迎え入れてくれました。食文化が自分に合うか不安だったので、東京の専門店でチェコ料理を食べてみたのですが、とてもおいしかったので何の心配もなく渡欧することができました。大学の関係者はもちろん、地元の人たちは日本人によく似た気質を持っていて、生活にまったくストレスを感じることはありませんでした。そんなチェコが大好きになり、帰国後、日本チェコ友好協会の会員になりました。
構造物の耐久性に大きく関与するコンクリートの引張特性
コンクリートの引張強度の研究とは。
コンクリートは基本的に圧縮に強い材料で、設計通りに工事をすれば、強度不足で不具合がおきることは滅多にありません。一方、コンクリートは引張強度が弱いためひび割れが発生しやすく、耐久性の低下を招きます。鉄筋コンクリートの場合、コンクリートが強アルカリ性のため通常は鉄筋はさびませんが、何らかの理由で鉄筋がさびるとその膨張圧により、コンクリート表面にひび割れが発生します。一旦ひび割れが発生すると、鉄筋はより一層さびやすい環境におかれ、結果として鉄筋コンクリートの耐久性が加速度的に低下します。そこで、ひび割れがどのように伸びていくのか、どのように隙間が開いていくのかをコンピューターシミュレーションで予測することは耐久性の予測の上でも重要となります。その際、コンクリートを実際に引っ張った試験から得られる引張特性のデータが必要となります。
どのような実験手法をとっていますか。
コンクリートの直接引張試験方法を提案するため、本学の名誉教授である秋田 宏 博士と独自の実験装置を製作しました。コンクリートは少しずつゆっくり引っ張った場合、急激に破断するのではなく、引張軟化がおきます。この実験装置により、引張軟化の正確な試験結果(引張特性)を知ることができ、耐久性の予測につながります。実験には、コンクリートの供試体を作成する必要があり、実験の条件に適した乾燥までの工程を含めると3、4カ月前から準備が必要です。実験そのものも1回につき4時間程度かかり、ひび割れ発生の様子などを目を凝らして観察しなければいけません。もちろん、各種センサーをつけてPCによるデータ採取はしますが、学生たちと試行錯誤しながら観察することに意義を感じています。
自身の研究が果たすべき目的とは。
現在、建設・土木事業でも脱炭素やカーボンニュートラルによる社会貢献が求められており、コンクリートの材料であるポルトランドセメントは大量の二酸化炭素を排出してしまうため、材料から見直そうという動きが盛んになっています。また、二酸化炭素を吸収するコンクリートの研究も進んでいるようです。耐久性をアップさせ長寿命化させるのも有効です。未来ある若者たちにとって、今後の環境問題は重要な課題です。私自身も、研究者として後世のために少しでも貢献していきたいと考えています。


将来の可能性に心躍らせながら未来を描けるホワイトボードを
教育者として課題に感じていることとは。
高度経済成長期に建設された多くのコンクリート構造物が設計耐用年数を迎え、大きな事故も発生するようになりました。今こそ、私を含めた都市工学の学術を修めた先達が技術者として知恵を尽くす時だと思いますし、都市工学分野を志望する学生たちをもっと増やさねばと感じています。
小出先生にとっての「未来のエスキース」とは。
研究活動はいつまでも可能ですが、大学教員としての仕事には期限があります。60歳を過ぎて、まるで将来の進路に思いを巡らせながら大学の4年間が始まる新入生のような心境にあります。何でも自由に描けるまっさらなホワイトボードを前にしている感じでしょうか。これまでのキャリアを活かす選択肢もありますが、また何か違った好きなことがこれからできるのではないかという期待感にも胸が躍っています。本学の学生たちには、自分が学んでいることを糧にホワイトボードへ自由に将来像を描いて欲しいし、そんな若者たちに習って、私自身も好きなようにこれからの行く先を描きたいと思っています。だから、私にとっての未来のエスキースは思い通り描けるホワイトボードのようなものでしょうか。
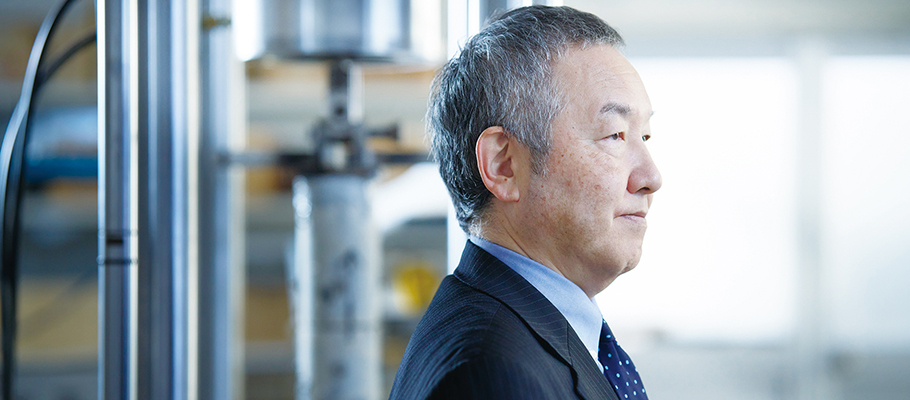
COLUMN

わたしと
チェコ
直接引張試験の縁でモラヴィアの大草原へ
チェコとは中欧のチェコ共和国のことです。チョコレートの話だと読み違えた方、良くあるミスです。このままお読み下さい。ちなみにチェコ人はチョコ好きです。2016年、コンクリート直接引張試験の縁で、日々の生活で日本人に会わないモラヴィア大草原を身近に臨むチェコのブルノに約9カ月間単身滞在しました。テレビ好きの私がほぼテレビ無しで暮らせ、ビールのおいしさと総合芸術オペラに目覚めました。食が変わり細胞・体質がすっかり入れ替わったのか、できやすかった口内炎も滞在以降一度もできてません。多くの経験、刺激を受けて帰国しました。やり投げの北口選手や野球の話題などでチェコに触れるととても嬉しいです。日本チェコ友好協会会員になったのも、チェコに貢献できればとの思いからです。ところで皆さんはどうか私のようにチェコ大使館宛に日本語でメールする際、「チョコ」と誤記しないようご注意ください。その他のチェコの話題は「チェコ通信」でネット検索、小出の記事を是非お読みください。