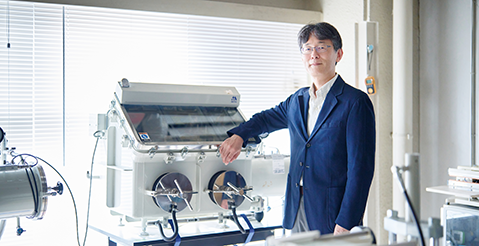PROFILE
1988年に大学を卒業後、民間企業などを経て、2008年に法政大学で博士(経済学)の 学位を取得。2011年に本学の工学部環境情報工学科の准教授に就任し、2014年に同学部環境エネルギー学科の教授に。2016年からライフデザイン学部経営コミュニケーション学科の教授となり、現在は学部長も務める。広瀬川創生プラン策定推進協議会の会長、宮城県プーメラン協会の代表としても幅広く活躍の場を得ている。
- 担当科目
- 環境経済学
- 法と経済学
- 環境関係法
- 組織の経済学
※教員の所属・役職は取材当時のものです。
THEME環境負荷を低減するための
法制度や社会システムを考察
THEME環境負荷を
低減するための
法制度や
社会システムを考察
豊かな社会の実現を目指して経済成長を続けてきたのと同時に、さまざまな環境問題に対峙する歴史を歩んできた近代日本。そんな複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に取り組むために、法や経済という視点から課題解決の方法を模索するのが、小祝先生が説く環境経済学です。持続可能な社会の実現を目標に掲げている今、学生にはまず身近な問題に目を向け、自らの経験から導いた考察を重ねる研究を指導。十分な知識と実力を養い、社会で活躍する人材の育成を目指しています。
2人の恩師が励まし支えた研究者を目指すモチベーション
環境経済学を学ぶまでの経緯を教えてください。
大学では法学部に進学し、憲法研究のゼミで学びました。卒業後、民間企業に入社しました。その後、環境に関わる新たな事業を進める際、自分が環境問題について知識が皆無だったことに気づきました。さらに、当時盛んな議論が行われていたまちづくりについても学びたいと思ったので、法政大学大学院の社会科学研究科に進みました。環境に配慮した経営が当然となっている今、大きく成長した分野になりました。
教員になったきっかけとは。
今でも付き合いが続いている憲法ゼミの恩師や、私が初めての弟子だという大学院の指導教官からの叱咤激励が、研究者の進路を望む自分を力強く支えてくれました。大学の教員は中学校や高校の先生と違って、大人の話ができる学生と時間、空間を共有できる面白さがあると感じています。大学を卒業してすぐ企業に就職し、家庭を持ちながら進学を志しましたが、尊敬する2人の先生たちのように最も社会と近い学生たちと語り合える世界に憧れていたのかもしれません。
経済と環境の関わりを理解しより良き未来へ向かうために
環境経済学とはどんな学問ですか。
かつては、経済活動は環境に負荷をかける主たる原因として、あまり良いイメージがありませんでした。しかし1970年代になると、日本の高度成長期が少し落ち着いていき、経済と環境の両立を考える気運が生まれました。公害問題が政治においても大きな課題となり国会で集中的に審議が行われ、いわゆる「公害国会」によって14の法律が改正されました。それ以前は、経済活動を阻害しない範囲で環境問題に取り組む「経済調和条項」が存在していたのですがほぼ削除され、経済と環境との調和を図る社会へ進んでいきます。それ以降、1980年代まで法律によって環境に関する規制が行われてきました。
国際的には、1972年にヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヵ国の先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)がCO2排出量に対して環境税を設けることを提唱したことで、環境政策における責任分担の考え方が各国で共通認識となりました。CO2削減に対する経済的なインセンティプ付与の考え方も浸透していく中、環境問題に対する政策や経済活動の考察を行う環境経済学としての学問が確立されていきました。
研究室ではどんな学びを行なっていますか。
経済学はもちろん、環境に関する法制度や歴史など学ぶべき分野は広範囲に及び、とても複雑です。この研究室では、文献や理論から学ぶことも重視しながら、学生にとって身近な事例に触れてもらうために、研究テーマの下で調査するフィールドワークも実践しています。私が会長を務めている広瀬川創生プラン策定推進協議会の取り組みとして、学生と仙台市職員、まちづくりコーディネーターで行う「広瀬川探索」は、地域を深く知るための良い機会になっていると感じています。また、本学と明治大学、法政大学の3つの研究室でテーマを共有して現地調査を行なった後、毎年12月に行う討論会も恒例になっています。視察の段取りや質問内容などすべて学生主体で行い、盛んな意見交換により環境経済学の観点で課題解決やまちづくりに関して考察を深めるのが目的です。

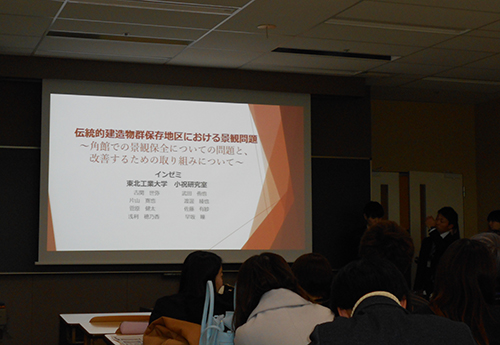
理論を学んで実践に勤しみ自らの夢を描ける確かな実力を
学生の指導で重視にしていることは。
学生たちには、私の大学院の恩師が語った「環境経済学なんていう学問は、いつか無くなるために我々はやっているんだ」という話をよくしています。COP(締約国会議)は30年以上も開催を続けていますが、いまだCO2排出量が大幅に減少する流れにはなっていません。これは、環境問題がいかに複雑な事情をはらんでいるかを示しています。だからこそ、若い学生たちには、自分で確かめて、自分で触れて、自分で考えることが大事だということを説いています。そして、考えるための武器として理論がある。理論を十分蓄えた上で、考える力を養ってほしいと話しています。
小祝先生にとっての「未来のエスキース」とは。
私が好きな小説に、喜多川泰著の「賢者の書」という名作があるのですが、その中に“そのとき人間が思い描く将来の完成図、それが「夢Jなのだ。”という一節があります。理想の最終形を描くのが夢だとするならば、その手伝いをすることが私にとってのエスキースでしょうか。学生はそれぞれ抱いている夢を自由に描けばいい。いまだ形を成していない未熟な夢に、輪郭を与えてあげるのが私の仕事だと思っています。

COLUMN

わたしと
環境問題
いまだ果たされない未来への約束
1992年5月、国連総会において「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択されました。この国際条約の目的は「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、現在及び将来の世代のために気候系を保護すること(環境省)」です。この目的達成のため、「気候変動に関する国際連合枠組条約締約国会議(以下「会議」という)」の第1回が、1995年ドイツのベルリンで開催されました。1997年の第3回では『京都議定書』によって先進国・地域の温室効果ガス削減の数値目標が採択され、第21回の『パリ協定』は『京都議定書』以来の数値目標が採択されました。
しかし、世界の温室効果ガス(GHG)の排出量は一向に減る様子はなく、「2010年~2019年の期間の年間平均GHG排出量は、過去のどの10年よりも高かった。(IPCC 第6次評価報告書)」ということです。1995年から2023年の第28回まで毎年開催(コロナ禍の2020年を除く)されてきた会議も、もうすぐ30年です。はたして将来世代への約束を達成できるのでしょうか。