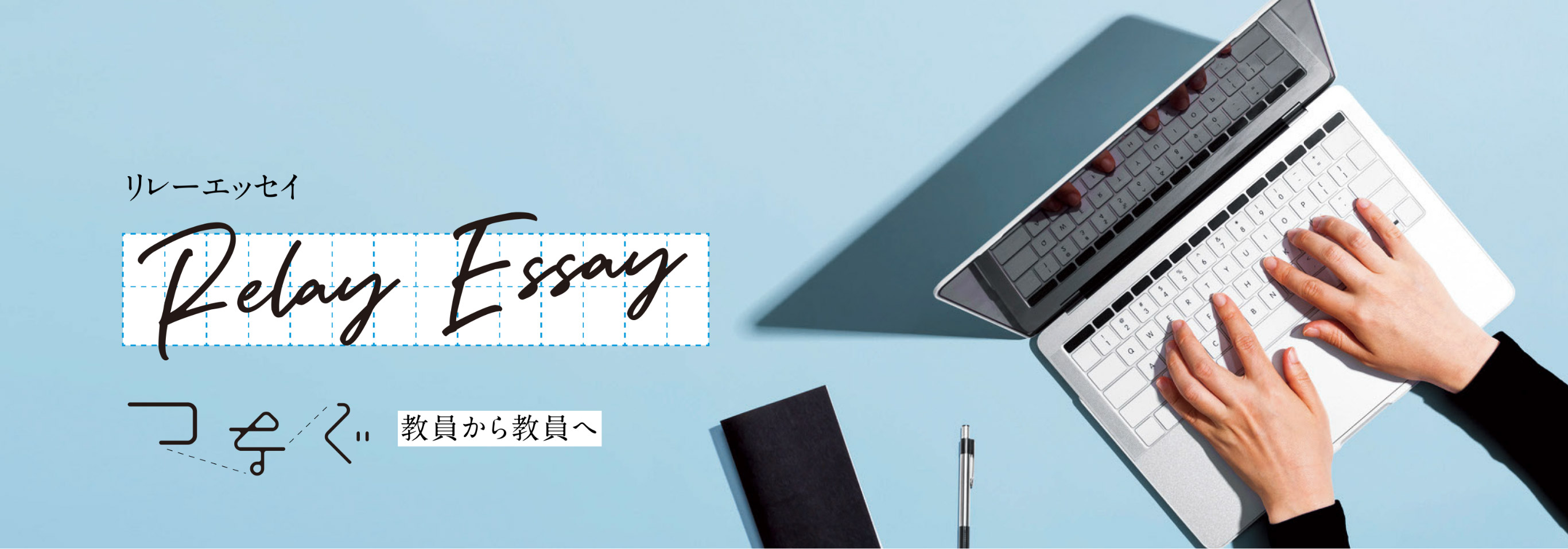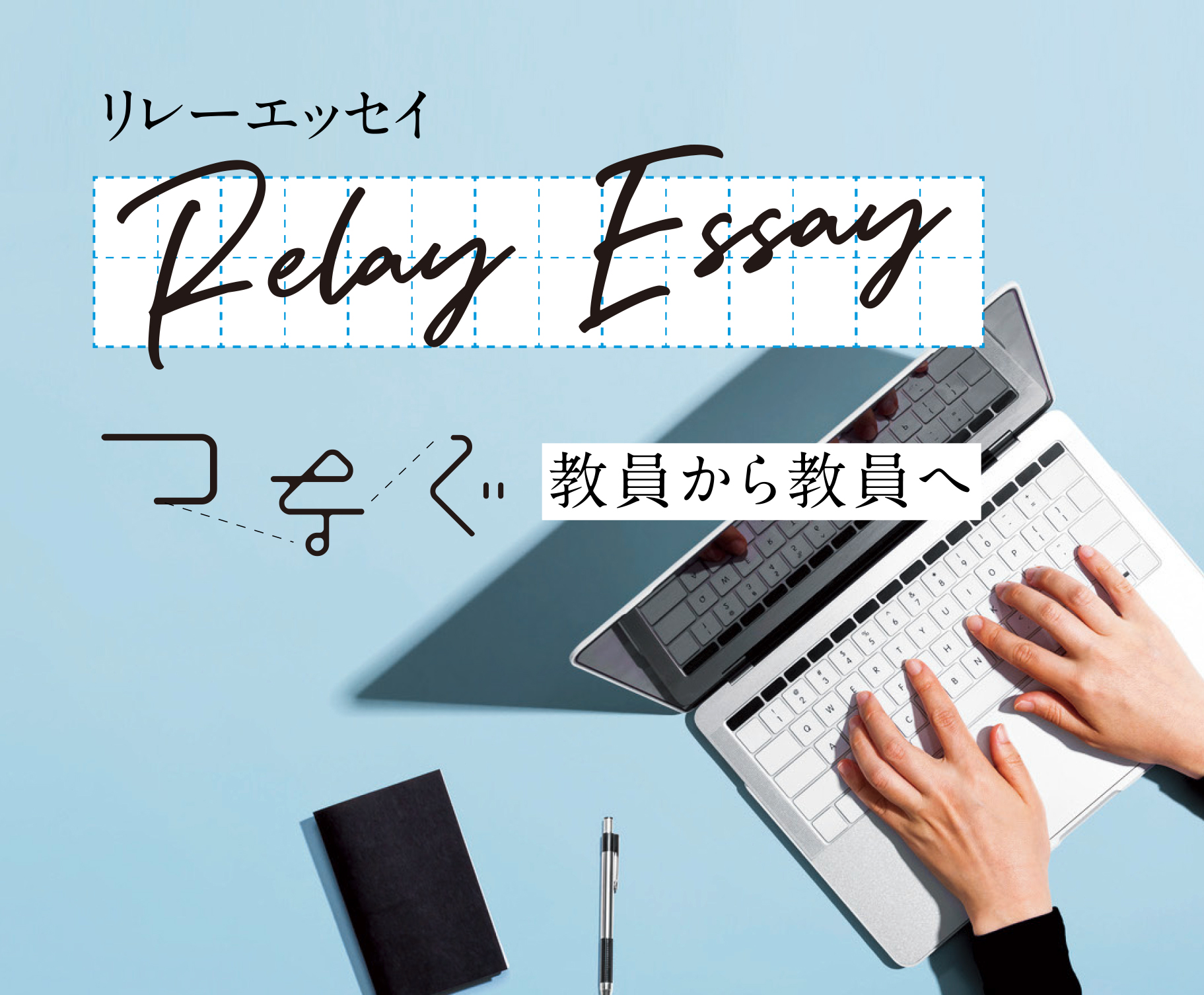大人から楽器を始めてみませんか?
VOL.078 鈴木 淳(総合教育センター)
楽器で楽しみませんか?
皆さん、最初の写真が何か分かりますでしょうか?分かる方は、すぐに「おおっ!」となると思いますが、普通はあまり目にしないと思います。読み進めていただくと最後に再び同じ写真が出てきますので、答えはそのときに。
ところで、学生の皆さんや教職員の皆さんの中にも、色々な楽器を演奏して楽しんでいる方が多くいると思います。僕もその中の一人です。現在は、主にヴァイオリンとチェロを弾いています。
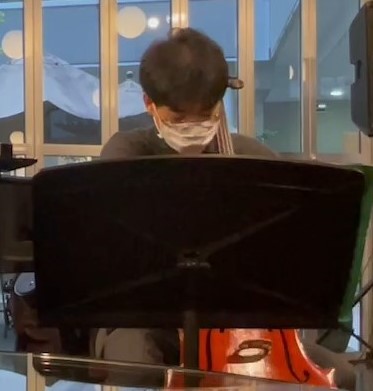
チェロの発表会での演奏です
「楽器の何が面白いの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は、楽器を弾く人の中には「演奏すること」もそうですが、それ以前に「楽譜」の収集や「楽器」のカスタマイズに関心を持っている方が多いと思います(おそらくは僕だけではないはずです)。これは、ヴァイオリンやチェロだけでなく、エレキギターやベース、または管楽器奏者の方にも共感していただけるのではないでしょうか。
今、ギターの話が出ましたので、少しエレキギターの話をします。僕は、大学時代はエレキギターを弾いていました。当時はサークルに入っていなくてもクラスにエレキギターを持ってくる人たちが多くいたので(90年代は海外のハードロックやヘヴィメタバンドブームでした)、僕も大学1年の春にエレキギターを買って(でも、アンプはお店の人が間違えてベース用を売られました)、毎日練習していました。大学にギターを持っていき、休み時間にギター好き同士で集まってミニアンプにつないで遊んでいました。また、休みの日は、友人たちで音楽スタジオを借りて練習。今では懐かしい思い出です。ですので、工大でギターを担いでいる学生を見ると、「がんばれー」と心の中で(または教室にギターを持って来ている学生には話しかけて)応援しています。
そんなギターですが、当時何が一番楽しかったかと言えば、演奏や練習もですが、毎月ギター雑誌を買って(今でも同じ雑誌が書店に売っています)、そこに掲載されている色々なメーカーのギターやアンプ、そしてエフェクターの広告やお気に入りの海外のバンドの記事を見ることでした。また、ギターショップにもよく行きました。でもお金はないので、結局100円のピックを3つくらい買って帰るのですが、それだけでも十分楽しめました。というのは、ピック一つにしても何種類もあって、硬さや材質、形もそれぞれ違い、自分に合うものがどれなのか、ギターを弾く人にとっては、まずここからが「楽しい悩み」です。また、エフェクター(音の効果を変える装置)についても色々あって、今はデジタルのマルチエフェクターが普通だと思いますが、当時マルチエフェクターは値段が高くて、代わりに安いものを少しずつ買い集めて個々のエフェクターを色々と連結させて使っていました。
クラシックからロックへ、ロックからクラシックに戻る
さて、現在へと移りましょう。では、なぜ今、僕がエレキギターではなく、ヴァイオリンとチェロを弾いているのかと言えば、もともと僕は小さい頃から高校2年までピアノとヴァイオリンを習っていました。一応、音楽大学を志望していましたが、高校2年でその道を断念しました。その後、ピアノを少し弾くことはあっても、ヴァイオリンのケースの蓋は27年間閉じたままでした。工大に来てからも、最初の約9年間は楽器を弾くこともなく、休日はほぼゲームをして過ごしていました(大型モンスターを制限時間内に一人で倒すのは大変でした)。しかし、ある日、昼寝をしているときに、偶然、僕が中学生の時の発表会の録音(懐かしいカセットテープ)を半分眠りながら聴くことになります。それまで忘れていた記憶でした。「なにこれ、メンデルスゾーンのヴァイオリンコンチェルト?え、昔の僕が弾いてるの、へー」(驚き)。

中学生の時に弾いていたヴァイオリン、今も練習で使っています
一気に眠気が吹っ飛びました。次の日、押し入れからヴァイオリンを取り出し、楽器店に持っていきました。ヴァイオリンなどは湿度管理をうまくしていないと接着部分の膠(にかわ)がはがれて楽器がばらばらになっていることも多いのですが、本当に運よく弾ける状態のままでした。その日から今日まで、再開してから7年くらいでしょうか、ほぼ毎日ヴァイオリンを弾いています。さらには、6年前にチェロも始めました。現在では、ヴァイオリンの友人たちとアンサンブルを組んで、年に数回、カラオケ部屋を予約して演奏して楽しんだりもしています。

チェロは持ち運びや置き場所が大変、でも楽しいですよ
ヴァイオリンとチェロの「楽しい悩み」
ところで、先ほどの楽器の楽しみ方の話に戻りますが、実は、ヴァイオリンやチェロの場合も、演奏以外に、「弦」や、弓に塗る「松脂」、楽器を構える際に用いる「肩当て」や、チェロの場合は「エンドピン」など、さまざまな付属品で楽しむことができます。ヴァイオリンやチェロを弾く人は、これらについて、「さて、どれを使おうか」と「楽しく悩む」わけです。たとえば、弦一つにしても、「スチール弦」、「シンセティック弦」、「ガット弦」というように、材料によって音質や弾き心地、そして耐久力が異なります。さらには、それぞれに関して各メーカーから数種類ずつ出ています。中には、楽器に張る4本の弦をそれぞれ違うメーカーのもので組み合わせる人たちもいます。僕も、3本は同じメーカーですが、一番高い音の弦は、金色の特殊な弦を使うことが多いです(音のキラキラ感がすごいです)。ヴァイオリンを弾く友人たちに会うと、それぞれ今使っている弦や松脂の話、そして次の発表会で弾く曲の話になります。このように、楽器を弾く人たちは、演奏していない時も普段から「楽器」の話で楽しんでいます。

答えは、松脂コレクションでした。さて、今日はどれをつけようかな?
正解や終わりのない「楽しい悩み」
今回は、「楽器演奏」ではなく、演奏以外での「楽器を用いた楽しみ方」を書いてみました。楽器は、簡単にすぐできるようになるというものではありませんが、まずは実際に楽器に触れて、楽器自体を楽しみながら練習することで、長続きして無理なくうまくなっていくのではないかと思います。最近は大学生や大人になってから楽器を始める方が多くなっていますが、本当にみんな楽しそうです。みなさん自分の楽器をとてもかわいがっていて、弦や松脂、さらには楽器や弓のグレードアップなど、日々楽しく悩んでいるようです。
皆さんも、楽器で楽しく悩んでみませんか?

鈴木 淳 教授
こんにちは、総合教育センターの鈴木淳と申します。研究専門分野は19世紀英文学になります。最近はヴィクトリア朝イギリス小説とクラシック音楽の関係について研究をしています。工大での授業は、主に1年生の「英語IA・IB」、そして2年生と3年生の「資格英語」、そして再履修の英語科目を担当しています。学生の皆さんにとっては「英語教員」との認識だと思います。でも、今回のエッセイでは、まったく英語は出てきません。今回の話題は、「音楽」に関する僕の昔話、そして現在の話になりますので、気楽に読んでみてください。