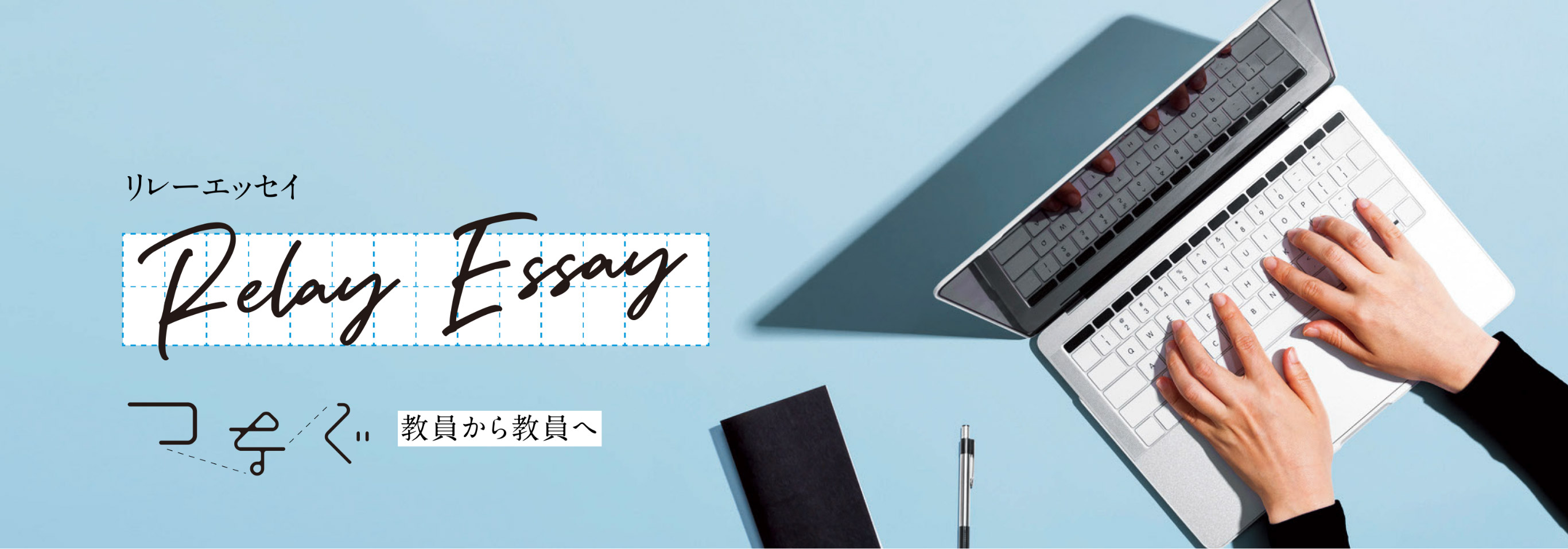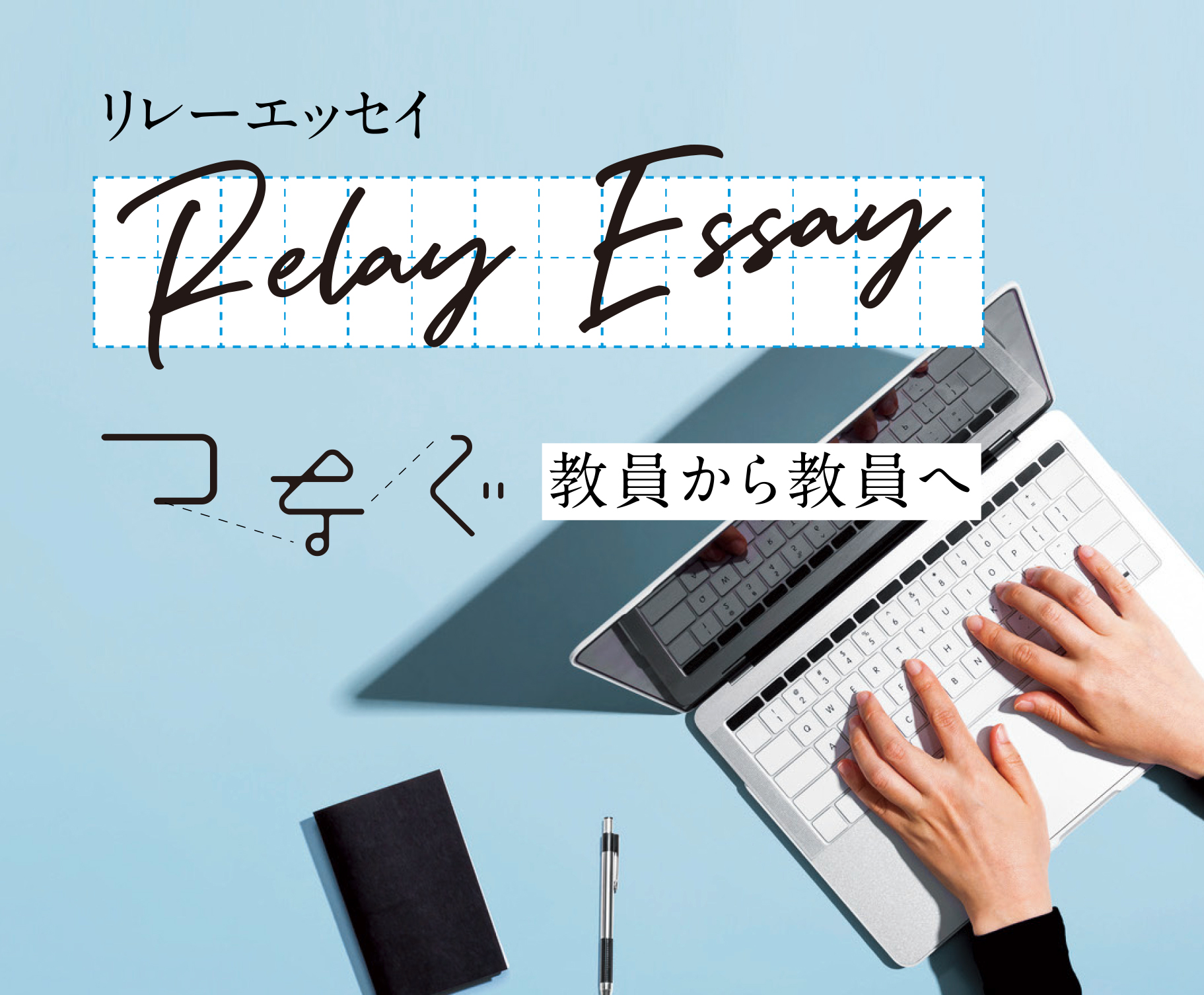人間の塔(Castells)という世界
VOL.076 畠山 雄豪(生活デザイン学科)
ところで、皆さん「人間の塔」はご存知ですか?
ゼミ生に写真を見せながら問いかけると、「よくわからないけどなんだかすごい組体操?」という回答が返ってきます。私も最初はあり得ないくらい高い段(9~10段!)にまで人々が組み上がっていく様子には圧倒されました。
18世紀末にスペインのタラゴナにて生まれたカタルーニャ人のアイデンティティと文化を力強く象徴するシンボルの一つで、2010年に世界無形文化遺産に登録されました。カタルーニャは言語的、文化的にも独特の圏域を持っています。

この写真はコンテンストの大会の時に当時のカタルーニャ州の首相が登場した時に掲げられたフラッグです。カタルーニャの結束力を示したものです(カタルーニャ独立運動にも関連します)。
最大の特徴は、老若男女だれでも参加でき、競争ではなく自分あるいはチームで共通の目標を達成する点にあります。コンテストの大会が2年に1回タラゴナにて開催されます(闘牛場をリノベーションした空間も注目)。この大会は、販売と同時に座席が完売してしまうなどカタルーニャでは非常に人気の大会です。

人間の塔はいくつかのパートに分かれており、一番上の部分はpom de daltと呼ばれ、その下が順にtronc、manilles、folreとなり、一番下の基礎土台の全てを支える部分はpinyaと呼ばれます。全ての人が協力し、信頼関係を持ちながら進めていく必要があります。なぜなら、一つのミスで大きな事故になるためです。
人間の塔は、決まった旋律の音楽(音楽隊もチームにいます)が鳴り始めたら開始の合図で、pom de daltが手を挙げたら完成形になります。その後、崩れずに塔が解体できたら「成功」となります。人間の力で成り立っているものなので、長い時間維持するのは難しいため、いかに「崩れずに」解体できるかがポイントです。焦って降りてバランスが崩れ「失敗」してしまうことがあります。しかしながら、pinyaがいるため、ある程度の衝撃は緩衝されます。
人間の塔のチームはカタルーニャ地方の各地域にあり(現在では海外にも)、それぞれの地域コミュニティにも大きな役割を担っています。何でもfer pinyaというカタルーニャ語は、人間の塔から生まれた言葉で「共通目的を達成するために力をあわせること」という意味だそうです。そのような言葉からもカタルーニャの地域性、市民性が出ているように感じます。
縁があって、2017年ごろより、早稲田大学の研究チームに加わり、バルセロナの人間の塔のチーム「Castellers de Sants」について調査(当方は撮影記録も兼任)を行っています。
チームを調査取材すると、平日にも関わらず、仕事終わったメンバーが夜に集まり、練習し、深夜まで飲みながら色々なことをディスカッションして帰っていきます(翌日は普通に出社!)。そのタフさに脱帽です。

学校に併設された練習場にてトレーニング。人間の塔専用の天井高、設備、安全ネットなどが設えられていて、建築的にも興味深い空間です。


大会直前の練習

人間の塔の上段を担うメンバーは子供や女性が多い


大技を決め、笑顔のメンバー
人間の塔という一つのコミュニティが地域性、文化性も含めて大事なものとして扱われていることがわかりました。
最近では、Santsの姉妹チームとしてCastellers de Tokyo(3’z)が発足し活動しています。応援よろしくお願いします!

Castellers de Tokyo(3’z)
色々振り返ってみると私の学生時代に比べて色々なことが調べやすい環境になったからこそ、2次情報だけでなく空間も人もコミュニティも実際に足を運んで五感で感じて解釈できるように努めていこうと思います。また、私自身、複数の軸の思考を持って色々な場所事象に向き合っています。
研究者として、教育者として、写真家として。
複数の軸を持ち、思考を主観的視点、客観的視点とキャッチボールしながら日々向き合っています。そのようなことが結局は自分にとって大事な視点となりました。
これからもゆらゆらとゆらめきながらも時には人間の塔のように目標に向かってチームで協力しながら歩んでいこうと思います。
なんだか取り止めのない話題提供となってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

畠山 雄豪 教授
専門は建築計画と都市計画です。東京で育ち、北海道大学にて学位取得後、都内の大学等を経て、2018年より着任しました。建築空間から都市に広がる事象を視覚的にとらえ分析しています。対象の内容としては、都市景観、都市の居場所、避難行動、復興まちづくりについて行っています。東北地方という場所は文化に富む場所なので、時間を見つけては色々な場所に身を置いています。また研究者という立場とは別に、写真家としても活動しています。

畠山研究室
「地域防災」という分野を建築計画面から取り組んでいます。「地域防災」は「より良いくらしづくり、まちづくり」において大切な視点です。そのためには、人間の行動、人々のつながり、空間づくり、まちづくりとミクロマクロな視点で考察することが必要です。当研究室では、施設やまちにおける行動から、地域のコミュニティ、視覚的なまちなみまで自ら取り組みます。ハードの対応だけではない、ソフトの対応を含めた本当の意味でのコミュニケーションをとることができる仕組みについて、人の避難行動、建築空間の使われ方から地域特性をとらえたまちづくり、景観評価へとミクロ・マクロに調査、分析を通して検証しています。