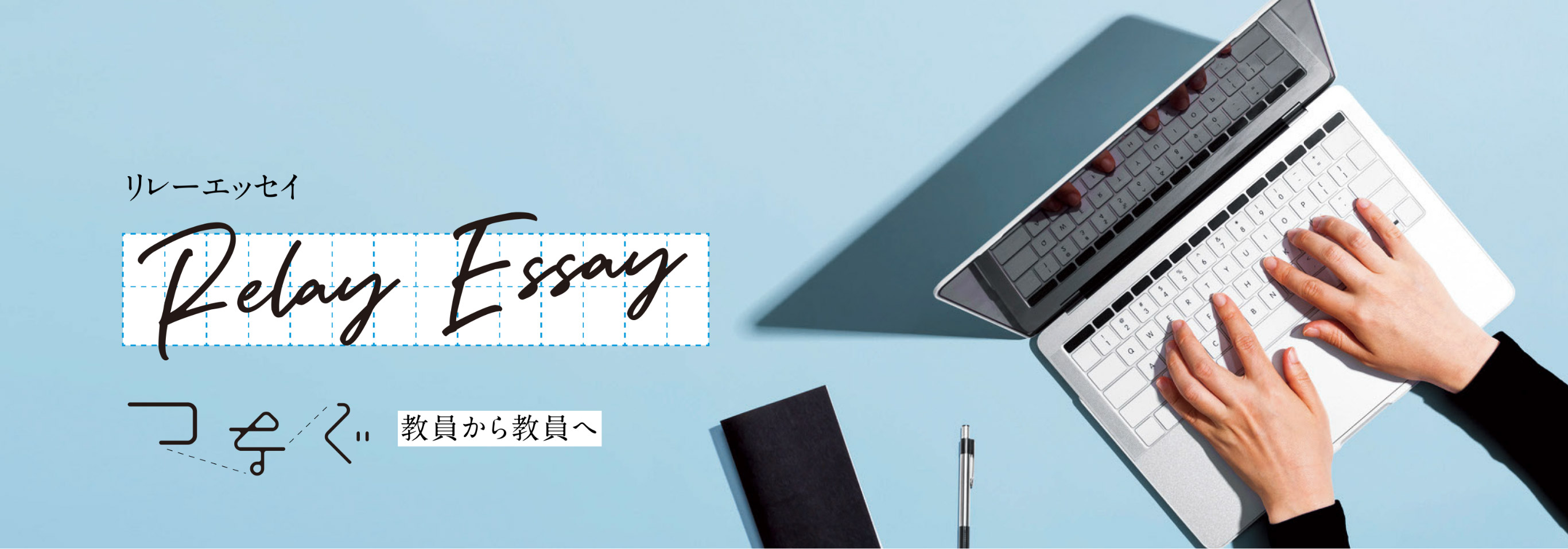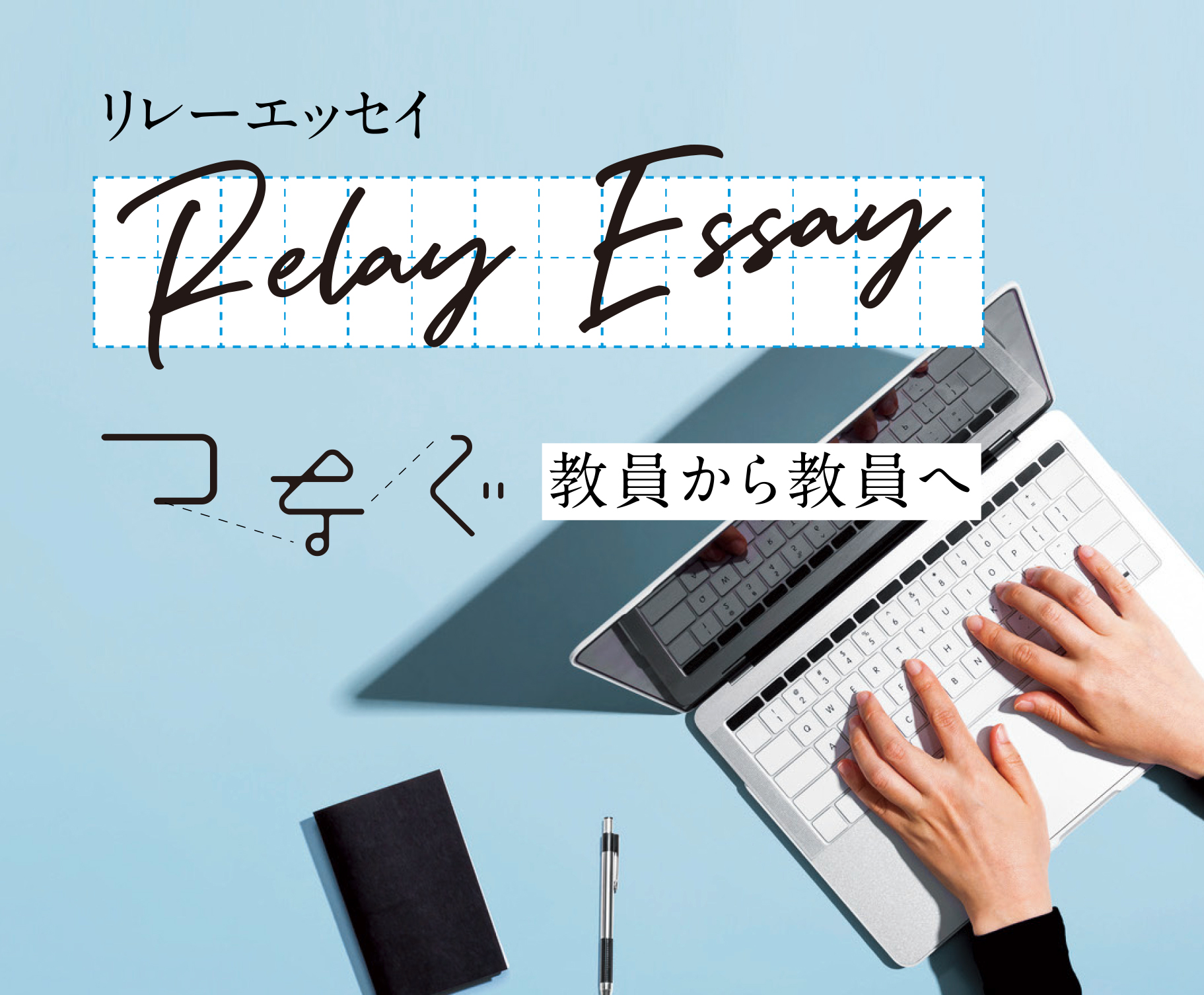雑感 2025.03.28
VOL.079 下位 法弘(電気電子工学課程)
つれづれなるまま、とりとめもなくその時に起こったor感じた事柄を「脈絡なく」書き連ねてみました。
① 宮城県で自動車解体業を担うMogee株式会社と共同開発している車載用廃蓄電池のリユースによるモバイルバッテリーを、企業版ふるさと納税として山梨県甲府市に納品するために2025年3月27-28日に現地まで赴きました。共同開発から納品に至る顛末はここでは特に述べませんが、甲府市に初めて訪問した私としては、街全体が「武田信玄」推しだと感じました(あくまでも個人的な感想です)。武田信玄は甲斐(山梨県)の守護大名・戦国大名であった(たしか)甲斐源氏の嫡流を持つ当主として戦国時代に活躍した武将であり、甲斐に加え、信濃・駿河・美濃などの一部を併合し領国をさらに拡大する基盤を築いた、あまりにも有名な戦国大名です。400年以上経た令和の時代まで愛されているのは、仙台における「伊達政宗」と似た立ち位置だな、と感じました。
ちなみに、その伊達政宗は戦国末期から江戸時代前期にかけて活躍した仙台藩初代藩主として現在の仙台の基盤を築いており、今でも仙台の各地に様々な逸話を残す「愛されキャラ」だな、と感じます。静岡県出身の私としては日本史で伊達政宗を知る程度で、最近(2025年3月)も再放送している大河ドラマ「独眼竜政宗」から伊達政宗の形跡をたどる程度の知見しか持っていません。
伊達政宗が有名なのは誰もが知るところだと思いますが、私個人としては、江戸幕府4代将軍徳川家綱から5代将軍綱吉の治世時代にかけて起こった「伊達騒動」にも非常に興味をそそられています。伊達騒動は、江戸時代前期に仙台藩伊達家で起こったお家騒動であり、黒田騒動、加賀騒動とともに「三大お家騒動」と呼ばれています。仙台藩3代藩主伊達綱宗から5代藩主吉村にかけて複数回起こった伊達家の内紛や改易(=お家取り潰し)されかけた一連の騒動をまとめて伊達騒動と呼ばれています。そこに江戸幕府や仙台藩の政治的徒党・派閥による権謀術数、そしてこの騒動を収めようと暗躍した仙台藩の家臣団に良くも悪くも人間味(腹黒さ?)を感じてしまい、興味の持てる歴史的事件だと思いました。しかし「伊達騒動」は、事件に関わる史跡や文書等の物的証拠がさほど残っておらず(仙台にどの程度残っているかわかりません。。)、さほど広くは知られていないのが残念です。ちなみに伊達騒動は山本周五郎著「樅ノ木は残った」等に記されており、大河ドラマとしても実は独眼竜政宗より前に放映されています(1970年放映)。

武田信玄像(甲府駅前)

伊達騒動が起きた酒井家上屋敷跡(千代田区丸の内)
② 2025年3月に我が娘が大学を卒業しました。数学がとても苦手な、典型的な文系人間であり、残念ながら本校とは縁がなかったのですが、無事に卒業してくれてひとまず安心しています。大学生になってから広い意味で福祉系の仕事に興味を持ったようで、医療系や福祉系の資格取得の勉強に励んでいました。そして、何事も現場経験が必要だと考え、国家資格を取得しながらまずは介護員として社会人をスタートさせるようです。自分が就職したときを思い起こすと、ここまで覚悟をもって将来を考えていただろうか、何となく茫漠とした人生を送っていたと思うのですが、彼女は少なくとも私に似なかったということでしょう。
ちなみに、医療施設等に入院した場合にかかる費用について、その医療費の家計負担が重くならないよう医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。私のまわりでも最近まで利用していた人がいました。その上限額は、年齢や所得に応じて定められており、さまざまな条件を満たすことで負担を更に軽減するしくみが設けられています。厚生労働省曰く、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じて負担する必要がある、とのことです。たぶんそれなりに医療費はかかっているにも関わらず、実費として個人が支払う医療費がある程度抑えられているのは、私でもコロナやインフルエンザ等で通院したときに実感しました。医療費の実費を抑えて国民全員が公平に高度な医療を受けるための「国民皆保険制度」は、日本にとって必要な制度だと思い、この制度を維持させるために保険料が(ある程度は)高額になってしまうのは仕方ないようにも(最近は)感じてしまいます。なお、高額療養費制度の負担上限額引き上げは全面凍結されました(2025年3月時点)。
③ 保険料に限らず、物価の高騰が止まらずに何かとカネがかかるご時世ですが、物価高騰の一因になっている円安の影響で、国内の中古車のほとんどが海外に流出しています。国産ハイブリッド(HV)車は海外で人気があり、搭載されている蓄電池が充放電機能を失ってもガソリン車として動くため、非常に重宝されているようです。日本は蓄電池等に含まれるレアメタルなど希少金属(=都市鉱山資源)の保有量は世界でもトップクラスだといわれています。この都市鉱山資源を国外に流出させないよう、蓄電池等に含まれるレアメタルを抽出して、新たな蓄電池の材料として再利用する、いわゆる循環経済(=サーキュラーエコノミー)を具現化するために車載用蓄電池のリユース技術を確立していかなくては、と強く思いました。

車載用バッテリーをリユースした大型ポータブル電源「おおポタ電」
以上のような全く取り留めもないコトを、甲府からの帰路の電車に揺られながら漠然と考えていました。

下位 法弘 教授
静岡出身の私は大学受験で初めて仙台に来ました。大学院修士課程修了後、ソニー株式会社で関東・東北で転勤しながら社会人ドクターで博士号を取得し、2011年に東北大学、2020年から東北工業大学に着任して現在に至ります。

機能性材料・デバイス創製研究室
「環境」をキーワードに、蓄電池の基礎研究から応用開発に至る材料開発と廃棄電池のリサイクル技術の開発、および炭素材料の物性研究および新規デバイスへの応用研究開発について主に2つのテーマの研究開発を促進しています。学生とは、研究活動を日々勤しんでいます。