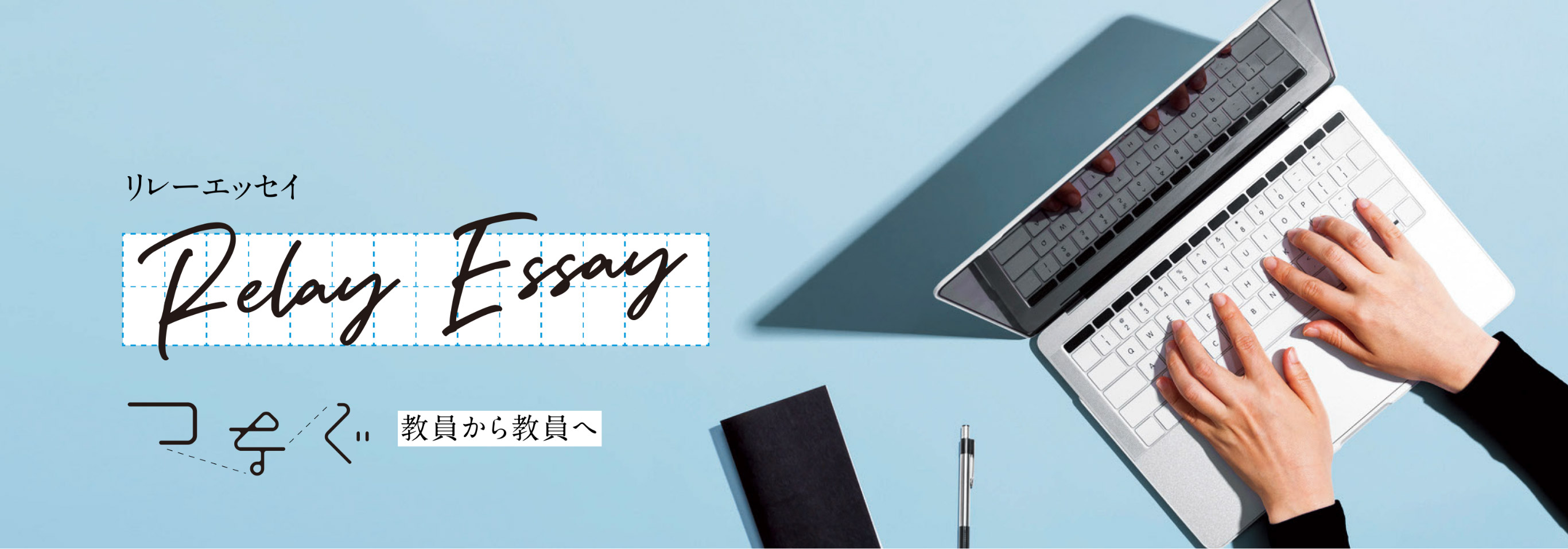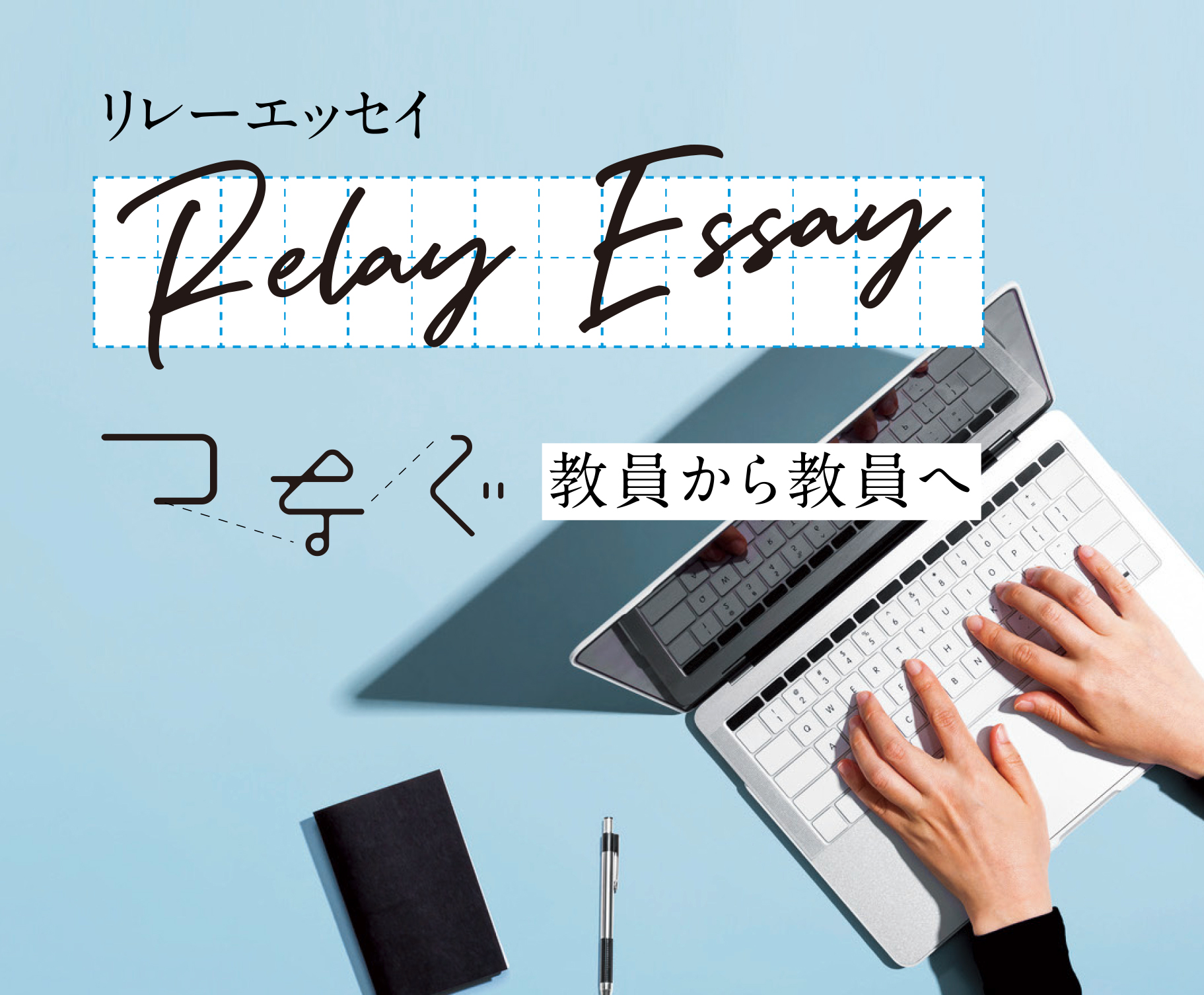日本からドイツ、そしてまた日本へのデザインの旅
VOL.077 籔下 聡希(産業デザイン学科)
東京で学生をしていた頃、祖母と二人で暮らしていた時期があり、良く祖母から祖父の話を聞かされていました。祖父は祖母と出会う前、確か1930年代頃、仕事の関係で10年ほどロンドンに滞在していました。ロンドンの街並みの中で欧州の人に混ざり、シルクハットにスーツ姿の祖父の写真を見ながら、いつか自分もヨーロッパに行ければと、漠然と夢を描いていた当時のことを昨日のように思い返すことができます。

父方と母方、それぞれの祖父から譲り受けたシルクハットと麦わら帽子
そしてそれから20年以上の月日が経ち、結果その祖父よりも長い17年という期間をドイツで過ごし、またドイツ人の妻、そして子供たちとの生活と、ヨーロッパにドップリと浸かった後、日本へ戻ってくることになりました。
日独の生活を何度も行き来していた頃、もちろんこれはドイツに親戚、友人がいるため、今でも当てはまるのですが、自分には並行して流れる二つの別の世界があり、そのどちらにも自分の関わる場があり、とても不思議な感覚だったことを覚えています。それは、日独と世界が変わる中で、まるで自分が二人いるような錯覚で、だからと言って、日本での自分とドイツでの自分の性格が変わるわけではありませんが。
そして、日本、仙台での暮らしも半年以上が過ぎ、17年のドイツ生活の後、日本の暮らしにも慣れ始めた中で、今回、今の自分だからこそ感じることができる、日常におけるこの今の日本での気づきをまとめてみました。ただそれはどちらが良い、悪いという比較ではなく、今の二国間での感覚の差を伝えるということで、国・文化の差がある中で、他を知ることで、己を知るという思いからです。
1.ゴミ箱がない、それでも街にゴミが少ない
今回、ドイツから帰ってきて驚いたことの一つは、街にゴミ箱がないことです。ゴミ箱をなくすことで、ゴミ回収のコスト削減という視点もあると思いますが、それはやはり「ゴミはゴミ箱へ」という日本人のモラルがあってできることです。ヨーロッパではなかなか考えられません。ドイツでは、ゴミ箱があるにも関わらず、ゴミが街中に溢れていて、そのために様々なアイデアが施されますが、なかなか上手くはいきません。例えば写真のドイツのハンブルグにあるゴミ箱は、ゴミ箱がゴミ箱の視点で話をしています。日本ではゴミ用の携帯ケースなども売られていて、自分が子供の頃は、そんなプロダクトはなかったと思いますが、社会の変化に合わせ、新たなプロダクトがいつも生まれてくるものです。

ドイツ、ハンブルグにあるユニークなゴミ箱。ゴミ箱がゴミ箱の視点で話をしています。
2.プラスチック・ビニール袋、そしてパッケージの量が多い
ビニール袋の消費について。これは日本はもっと意識する必要があると感じていまして、ドイツでは、布製の買い物袋をほぼ誰もが常備していて、買い物の時に利用しています。ビニール袋を利用する習性はほぼありません、もちろん普通に買うことはできますが。ただ自分はこの布製の袋を集めすぎて、時に家族に怒られていました。というのも、グラフィックが格好良いものが多く、そこに惹かれてつい衝動買いをしていました。
時々、このようなドイツのエコバッグを日本のセレクトショップで見るのですが、やはり人は他の文化のモノに興味を惹かれるものです。
また海外の方が日本に来て、驚くのは、もちろんゴミが街に少ないということ、次にビニール袋の多さです。最近もドイツから友人がきていたのですが、やはり、このビニール袋の多さには驚いていました。
ただ、最近はビニール袋は無料ではなく、購入するようになってきているので、今後はここに対する意識も変わってくると思っています。
それでもスーパーや、コンビニ、薬局でのプラスチックのパッケージの多さには常に違和感を覚え、日本の美意識の一つでもある、美しく包む文化とも関係してくるのですが、ただ特にパッケージに関しては、ドイツでは、野菜や果物は、そのまま持ち帰るのは当たり前で、そもそもなぜそれにパッケージが必要なのか?と考えてしまいます。
もちろん衛生面からという意見もありますが、それは水で洗えば良いわけです。
3.自転車の走行方法のマナー
ドイツのみならず、ヨーロッパでは、自転車の利用が盛んで、ちょっとした通りには、ほぼ必ず自転車専用の道があります。
日本も時折あるのですが、そもそもその利用方法がバラバラで、左通行なのか?右通行なのか?そんな基本的なことすら聞きたくなります。ドイツでそんな走り方をしていたら、すぐに文句を言われますので。
またドイツでは、小学校で自転車の正しい乗り方、またマナーを学ぶ授業があり、課外授業の一環として、先生と一緒に自転車を乗って街中を走り、自転車マナーのテストを行うこともあります。

子供たちも自転車で小学校へ
4.歩きスマホの人の多さ
ドイツでも、もちろん歩きスマホは大きなテーマですが、この度の日本でのその異常の人の数に日々驚いています。
毎日、仙台での自転車通勤の際、前を見ずにスマホ歩きする人にいつも危険を感じています。
これは大人のみに関わらず、小さな子供がスマホを利用している姿も多く見え、ドイツではスマホ利用に関しては、学校などで、両親を対象にしたセミナーなどが開催されるなど、利用時間、それによる影響などを注意、考慮して、各家庭でその使用を制限しています。
5.地震のある日々。天災が日常に起こり得る生活と自然に対する感覚。
避難訓練というものを今年、何十年ぶりにやりました。
またそれとは別に、実際に講義中にちょっとした地震があり、最初自分は全く気づかず、学生から地震ですと言われ、一瞬どう対応すべきか?迷いました。
皆に机の下に隠れるよう指示しようとしましたが、幸いそこまで大きくなく、ただ実際に大きな地震が起きた時はどうすべきなのか?考えさせられるものでした。
ドイツでは避難訓練というものがありません。というのもそもそも天災がありませんから、それに備える必要もありません。
日本はその自然条件により、台風や豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国です。そして、自分の子供たちは地震、天災をほぼ経験したことがなく、今回その地震が起きた夜、初めての地震に驚きながらも、ただただ初めてのその不思議な感覚を言葉にしていました。
天災と共に生きてきた日本人は、その自然を敬い、その自然に生かされている感覚が昔からありますが、ヨーロッパ、特にドイツにはない感覚です。

ドイツにみる一般的な自然の風景。荒々しい山々などは少なく、草原のような景色が広がっている。
6.日常にある広告量の多さ
日本の街中に見かける広告量には、常に圧倒されます。人に情報を伝えるための広告が溢れすぎて、結局人はその情報量多さにその情報を遮断することになります。
ドイツでは、景観保護のために広告規制がなされていて、基本的に広告は広告スペースのみにあり、街中には、広告スペースの柱など(アナログ・デジタル)が設置されています。

地下鉄に用意されている広告スペース。格好良いグラフィックにはいつも目を引かれます。
最後に、先月のある日、小学生の息子と二人で歩いていると、突然彼が、ここ日本はまるでドイツにいるようだと、話し始めました。
基本的に日独の生活水準は近く、学校の先生や友人との距離感にドイツと似たものを感じていて、ただ言語だけが異なると、楽しそうに話していました。そして、最近書いていた卒業文集(半年の小学校生活でもう卒業!?、そして漢字を含めた日本語で書き始めている)では、今ここでの生活が楽しく、ハンブルグに戻る必要性を感じていない、と書き締めていました。
ドイツから日本へ来る前は、子供たちがその変化に対応できるか?と心配していましたが、その変化を楽しむたくましさを見せてくれているその子供たちの姿に正直、ホッとしています。
日本からドイツを経由して再度日本へ舞台を移したこの旅は、まだまだ始まったばかりで、今後もその「特別」な日常を楽しんでいければと思っています。

去年のクリスマスは、ハンブルグにて例年同様に家族と過ごす

籔下 聡希 准教授
専門はプロダクトデザインです。
ドイツの美術大学にてインダストリアルデザインを学び、その後ドイツでデザイナーとして活動し、2024年に日本へ戻ってきました。17年過ごしたドイツでの経験をベースに、人に寄り添った、そして素材を活かした機能的なデザインを追求しています。

籔下研究室
変わりゆく時代の中で、デザイナーには様々な能力が求められています。素材の特性、製造技術を学び、創造力を養い、表現力を鍛えていく、その中でもヒトとモノの関係性を新たな視点で見つめ直すことで、自分にしか見えない風景を描き出し、これからの製品デザインの可能性を探っていきます。