CADの基本操作と建物の仕組みを習得

1年次/建築CAD
作図システム・CADを使用し、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物を描く実習形式の授業です。実際の制作現場で多く利用されているCADの基本操作を習得することができます。また、形態と構造という2つの側面から建物の基本的な仕組みを理解し、建築形態をデザイン、表現する技術を身に付けます。
2020年4月、現「工学部 建築学科」は
「建築学部 建築学科」として新たなスタートを切ります。

建築学科の特徴的な授業を紹介します。
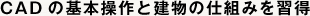

作図システム・CADを使用し、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物を描く実習形式の授業です。実際の制作現場で多く利用されているCADの基本操作を習得することができます。また、形態と構造という2つの側面から建物の基本的な仕組みを理解し、建築形態をデザイン、表現する技術を身に付けます。
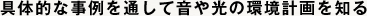

建物には、適切な音響と採光が不可欠です。この授業では、生活の場に適した静けさの確保と適切な響きの調整、日照の仕組みなど、音・光環境の概念と技術について学びます。屋内設備機器マンションの隣戸からの騒音といった具体的な事例を基に、問題の解決法や建物環境計画の立て方などを考察していきます。
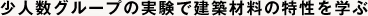

さまざまな材料について少人数グループで実験します。コンクリート、鋼材、木材の破壊試験や、ボード類の耐水性、難燃性、耐衝撃性などの試験を行い、構造の安全性にかかわる材料の性質を、実験を通して身に付けることができます。実験で得たデータを整理し、発表する能力を高めることも重視します。
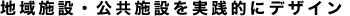

2つの地域施設・公共施設の設計(教育施設、文化施設)を通じて、地域における公共施設の機能と規模の関係を理解します。また、建物の外部空間の構成、ランドスケープや植栽、広場などの概念を理解するとともに、空間の規模、機能に対応する架構方法について適切に判断する方法や地域課題をとらえる中での施設計画のあり方、地域社会や地域生活と施設計画・デザインの関わりとそのあり方を学んでいきます。
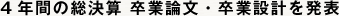

建築学研修Ⅱで提出した成果をさらに展開し、それぞれのテーマについて研究や設計の知識を深めます。最終的には、4年間の集大成ともいえる卒業論文または卒業設計をまとめ、その成果は研究報告や調査報告、設計作品として卒業研修報告集に掲載されるほか、せんだいメディアテークで公開発表会も行われます。
最終更新日 2020年3月31日